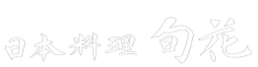季節のご案内
店主からのご挨拶

4月(卯月)です。
朝晩はまだ寒い日がある長野市です。
日中は暖かく3月に桜が咲き始めてしまうのではと思うほどの温かさがあり、雪が降るほどに冷え込む日もありの気温の高低差が凄い月でした。
長野市内ではそろそろ桜の花が咲き始める頃です。
今年はお花見で善光寺周辺が賑わうと良いですね🌸
依然としてまだまだ新型コロナウイルスの影響が大きいですが、少しずつコロナから通常の日常に戻っていけるような雰囲気ですね!
どうか無事にコロナが終息していくことを願っております。
さて、コロナで3年間休止しておりました旬花落語会を今月から再開する運びとなりました。
再会を待っていて下さったお客様本当にお待たせ致しました。
4月20日に入船亭扇辰師匠をお迎えして旬花落語会スタート致します。
大将のおはぎの4月限定は「桜餡おはぎ」です。
是非お召し上がりください。
季節の変わり目ですので寒い日もまだまだございます。風邪などひかれませんようお気を付け下さい。
今月は「田酒 特別純米 (日本酒・青森)」「耶馬美人 (焼酎・大分)」をお勧めしております。
本坊酒造の「駒ヶ岳」と「岩井 シェリーカスク」と「ラッキーキャット」も入荷致しております!
ハイボールをおすすめしております!
是非ご賞味下さい

陰暦 卯月(うづき)4月の由来
四月は、「卯の花」=「卯の木」(ウツギ)が転じて「うづき」になったとの説があります。
万葉集の歌では、卯の花、ホトトギスなどは初夏の季語として良く使われます。
歌は季節の先取りをしますから結局は今の春になるそうです。
卯の花(ウツギの花)が咲く季節なので
「卯の花月」の略とする説が有力とされています。
その他の説では、卯月の「う」は「初」「産」を意味する「う」で一年の循環の最初を意味したとする説や、
十二支の四番目が「卯」であることから干支を月に当てはめ、卯月になったとする説があります。
端午の節句
端午(たんご)の節句は、奈良時代から続く古い行事です。
端午というのは、もとは月の端(はじめ)の午(うま)の日という意味で、5月に限ったものではありませんでした。しかし、午(ご)と五(ご)の音が同じなので、毎月5日を指すようになり、やがて5月5日のことになったとも伝えられます。
そのころの日本では季節の変わり目である端午の日に、病気や災厄をさけるための行事がおこなわれていました。古く中国では、この日に薬草摘みをしたり、蘭を入れた湯を浴びたり、菖蒲を浸した酒を飲んだりという風習があったことから、日本の宮廷でもさまざまな行事が催されました。厄よけの菖蒲をかざり、皇族や臣下の人たちには蓬(よもぎ)などの薬草を配り、また病気や災いをもたらすとされる悪鬼を退治する意味で、馬から弓を射る儀式もおこなわれたようです。
端午が男の子の節句になった訳は?
古来から行われていた宮廷での端午の行事は、江戸時代にはいると、5月5日は徳川幕府の重要な式日に定められ、大名や旗本が、式服で江戸城に参り、将軍にお祝いを奉じるようになりました。また、将軍に男の子が生まれると、表御殿の玄関前に馬印(うましるし)や幟(のぼり)を立てて祝いました。
時代の変遷のなかで、薬草を摘んで邪気をはらうという端午の行事が、男の子の誕生の祝いへと結びついていったと考えられます。やがてこの風習は武士だけでなく、広く一般の人々にまで広まっていきます。はじめは、玄関前に幟や吹き流しを立てていたものが、やがて厚紙で作った兜や人形、また紙や布に書いた武者絵なども飾るようになっていったのです。さらに江戸時代の中期には、武家の幟に対抗して、町人の間では鯉のぼりが飾られるようになりました。